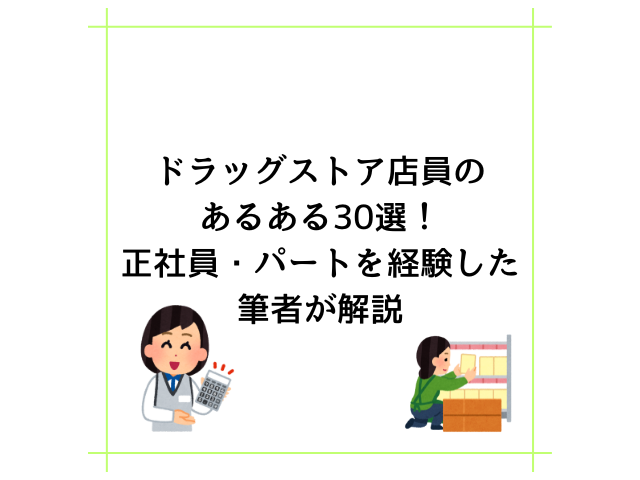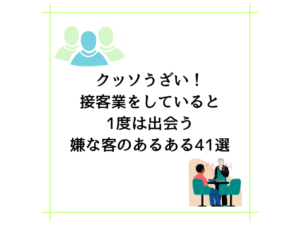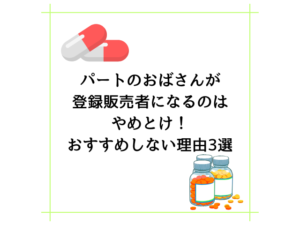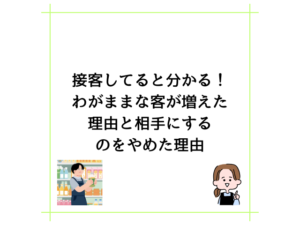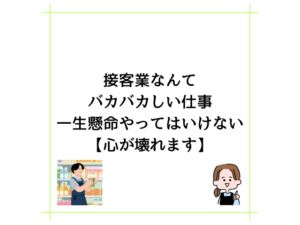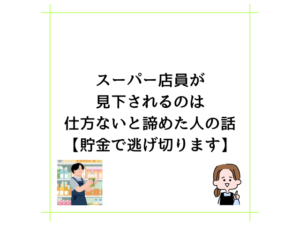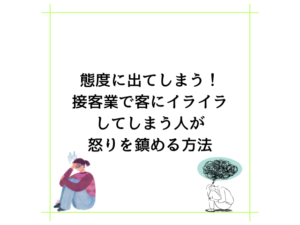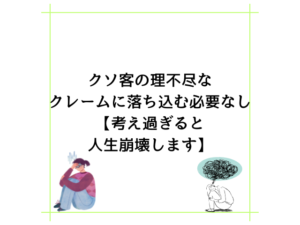毎日、商品の山とお客様の波に揉まれながら、ふと「これって、うちだけ?」と思うこと、ありませんか?
実はそれ、「ドラッグストア店員あるある」なんです。
筆者は正社員として店長まで経験し現在はパートとして働いている、生粋のドラッグストア店員。
この仕事の楽しさも大変さも、人一倍知っているつもりです。
この記事では、そんな私の経験から厳選した、思わず「わかる!」と声に出してしまうようなあるある30選を紹介します。
ドラッグストア店員のあるある30選

ここではドラッグストア店員のあるあるについて以下のカテゴリ毎に解説していきます。
- レジ編
- 品出し・在庫管理編
- お客様対応編
- 店内放送・アナウンス編
- その他・人間関係編
レジ編
ポイントカードの確認が、もはや口癖
「ポイントカードはお持ちですか?」
これはもはや、ドラッグストア店員の第二の挨拶。
どんなお客様に対しても、商品をスキャンする前に無意識にこの言葉が出てしまいます。
レジを離れてコンビニで買い物をする時でさえ、店員さんがポイントカードについて聞いてこないと、なんだか物足りなく感じてしまうほど。
もはや条件反射。しかし、まれに「結構です」と答えたお客様に、反射的に「ありがとうございます」と返してしまうことも…。
そのたびに、心の中で「あ、間違えた!」と小さく焦っています。
小銭を計算する「レジ脳」が発達する
お会計時に、お客様が小銭をたくさん出されたとき、一瞬で合計金額を計算する能力が身につきます。
「10円玉が3枚、5円玉が1枚、1円玉が4枚…合計39円。ああ、あと10円足せばお札だけでお釣りが渡せるな」と、脳内で高速計算が始まります。
これが毎日続くことで、もはや暗算は特技に。
レジから離れても、日常生活で買い物をするとき、お釣りをどれだけ減らせるか無意識に計算してしまう、まさに「レジ脳」が発達します。
「袋、結構です」と言われた瞬間の、あの焦り
お客様が「袋、結構です」とおっしゃったにもかかわらず、手が勝手に動いて、商品を袋に詰めてしまうことがあります。
特に、レジが混雑している時や、疲れている時にやってしまいがちです。
お客様が「あ、いや…」と困った顔をされると、「申し訳ありません!」と慌てて商品を袋から出し、何事もなかったかのように会計を続行。
その一連の流れは、さながら無言のコント。
お客様も「まぁ、いいか」と微笑んでくれることが多いですが、心の中では「やらかした…」と冷や汗をかいています。
バーコードが読み取れないときの、あの絶望感
どんなに慣れても、時々頑固に読み取りを拒否するバーコードに出くわします。
商品が古かったり、パッケージが傷んでいたり、時にはバーコードがどこにあるか分からない謎の商品も…。
お客様は後ろに並んでいて、プレッシャーは最高潮。何度もスキャンを試み、それでもダメなら手入力。
商品番号を打ち込む作業は、まるで暗号解読のよう。
そしてようやく会計が終わると、まるで高難易度のミッションをクリアしたかのような達成感を感じます。
「レシート、いりません」の裏で繰り広げられるドラマ
レジ袋に商品を詰めている最中に、「レシート、いりません」と言われることがあります。
もちろんレジからレシートを出すのですが、そのタイミングが絶妙に難しい。
お客様の「いりません」の声に反応して、素早くレシートをちぎり、ゴミ箱に捨てる一連の動作は、まさに熟練の技。
しかし、レシートを出すのが遅れると、お客様が去り際に「あ…」と気まずい顔をされることも。
一見単純なやり取りの裏側で、こんなにも時間との戦いが繰り広げられているのです。
「〇〇のポイント、貯まってますか?」への対応
「〇〇のポイント、貯まってますか?」と聞かれたとき、一瞬「はて?」となります。
お客様が言いたいのは「〇〇カードはお持ちですか?」ということだと理解していますが、つい反射的に「〇〇カードをお持ちですか?」と聞き返してしまうことがよくあります。
お客様も「ああ、はい」とカードを出してくれますが、この微妙なやり取りが毎日何回も繰り返されると、一種のジレンマに陥ります。
お客様の意図を汲み取りつつ、正確な言葉で対応する、その瞬時の判断力が求められます。
閉店前の、あの独特な静けさ
閉店時間が近づくと、店内から少しずつ活気が失われていきます。
お客様もまばらになり、店内にはBGMだけが静かに流れる時間。
この「閉店前の独特な静けさ」は、ドラッグストア店員だけが味わえる特別な瞬間です。
陳列棚を整えながら、明日の準備をしたり、掃除をしたり。
一日が終わりに向かう安堵感と、明日への期待が入り混じった、どこか物悲しくも心地よい時間です。
品出し・在庫管理編
在庫がない商品の「裏にありますか?」問題
お客様に「この商品、裏にありますか?」と聞かれると、たとえ在庫がないと分かっていても、一度は裏に探しに行くのがお約束。
「在庫確認してきますね」と言ってバックルームへ行き、何もない棚を眺めてから戻り、「申し訳ありません、在庫がございませんでした」とお伝えします。
この「裏に行く」という動作は、お客様への誠意を示すための大切な儀式。
たとえ無駄な往復でも、このひと手間が、お客様の納得につながるのです。
新商品が次々と押し寄せる、まるで波のよう
毎週のように次々と入荷する新商品。
入荷日は、まるで新商品の津波が押し寄せてくるようです。
棚のスペースを確保するために、既存商品の陳列を工夫し、時には在庫を減らす必要も出てきます。
新しい化粧品や日用品、食品などが段ボールいっぱいに届き、それを一つ一つ丁寧に品出ししていく作業は、まるで宝探し。
新商品の香りをこっそり嗅いでみたり、どんな商品なのかラベルをじっくり読んでみたりするのも、ちょっとした楽しみです。
店内で出会った同業者への、謎のライバル心
他店のドラッグストアの制服を着た人が、自店に買い物に来ているのを見かけると、なぜか「負けられない!」という謎のライバル心が芽生えます。
普段以上にキビキビと動き、品出しも迅速にこなし、レジでの対応も笑顔を多めに。
心の中では、「うちの店はこんなに綺麗で品揃えもいいんだぞ!」と無言のアピールをしています。
同業者同士、お互いの店舗の様子を探り合っているのかもしれません。
高いところの商品を取る時の、アクロバティックな姿勢
天井近くに陳列された商品を取る時、脚立が近くにない場合は、他の商品の陳列棚に足をかけて、アクロバティックな姿勢で手を伸ばします。
「ああ、もうちょっと…!」とつま先立ちになり、全身のバランス感覚を駆使して商品に手を伸ばす姿は、さながら曲芸師。
運悪くその姿をお客様に見られると、少し気まずいですが、目的の商品を無事手に取れた時の達成感は格別です。
賞味期限切れ間近の商品を見つけたときの、あの焦り
品出し中に、棚の奥から賞味期限が間近に迫った食品や飲料を見つけたときの、あの冷や汗。
すぐに気づいて手前に陳列し、値引きシールを貼るなどの対応をしますが、もしお客様の手に渡っていたら…と考えるとゾッとします。
期限切れ商品を出さないように、常に棚をチェックするのですが、見落としがないかヒヤヒヤする瞬間です。
お客様対応編
「〇〇ってありますか?」で始まる、商品の場所当てクイズ
お客様が「〇〇ってありますか?」と尋ねてこられたとき、その「〇〇」が薬なのか、日用品なのか、それとも食品なのか、一瞬で判断しなければなりません。
特に、商品名が曖昧な場合や、正式名称ではない俗称で呼ばれると、脳内で全商品を検索して回答を導き出す必要があります。
まるで、お客様から出される謎の商品クイズに挑戦しているかのようです。
「この薬、効く?」と聞かれて困る
お客様に「この風邪薬、よく効く?」と聞かれると、答えに窮します。
薬剤師ではないので効果を断定することはできませんし、「効きますよ!」と安易に答えるわけにもいきません。
そんなとき、私たちは「お客様の症状や体質によって効果は異なりますので、ご心配な場合は薬剤師にご相談ください」と、慎重に言葉を選びます。
このやり取りは、ドラッグストア店員にとって、接客スキルが試される試練の一つです。
商品の場所を指さしで案内するときの、あの葛藤
商品の場所をお客様に聞かれたとき、「あちらです」と指をさすか、それとも一緒に棚まで案内するか、一瞬迷います。
指さしで済ませてしまうと、お客様が迷ってしまう可能性も。特に、店内が広い店舗では、一緒に案内するのが親切ですが、レジが混んでいたり、他の業務が立て込んでいたりすると、そうもいきません。
瞬時に状況を判断し、最適な対応を選ぶ、接客のプロとしての判断力が求められます。
「これ、どうやって使うの?」と聞かれて、必死に商品説明を読み込む
お客様から、商品の使い方について質問されたとき、自分自身もその商品について詳しくないことがあります。
そんなとき、私たちは商品を手に取り、パッケージの裏面にある小さな文字の「ご使用方法」や「成分」を必死に読み込みます。
お客様には「少々お待ちください」とお伝えし、まるで初めて読むかのように真剣な表情で説明文を読み解き、的確な回答を導き出します。
突然始まる、健康相談室
お客様の中には、商品に関する質問だけでなく、自身の健康状態や悩みを相談してくる方がいらっしゃいます。
「最近、よく眠れないんだけど、どんなサプリメントがいい?」や「膝が痛くて…」など、時には個人的な悩みを打ち明けられることも。
私たちは専門家ではないので、あくまで一般的な情報提供に留め、必要に応じて薬剤師の先生につなぐようにしていますが、お客様の心に寄り添う姿勢は大切にしています。
店内放送・アナウンス編
自分の声が響き渡る店内放送に、恥ずかしくなる
店内放送で「いらっしゃいませ!」や「本日のお買い得商品をご案内いたします!」とマイクに向かって話すとき、自分の声が店内に響き渡る瞬間に、なんとも言えない恥ずかしさを感じます。
特に、声が上ずってしまったり、噛んでしまったりすると、余計に恥ずかしい気持ちになります。
しかし、何回も繰り返すうちに、堂々とアナウンスができるようになり、いつしか自分だけの「アナウンス節」が身についていきます。
自分のアナウンスに、誰も反応してくれない悲しさ
心を込めて「いらっしゃいませ!」と店内放送で挨拶をしても、お客様から特に反応がないことがほとんどです。
当たり前のことなのですが、時々、誰も聞いていないのではないかと、少し悲しい気持ちになります。
しかし、たまに小さな子供がマイクに向かって「いらっしゃいませ!」と返してくれたり、お客様が笑顔で会釈してくれたりすると、この仕事をしていてよかったと心から思える瞬間です。
その他・人間関係編
社員割引で、ついつい買いすぎてしまう
ドラッグストアで働く特権といえば、社員割引。
日用品や化粧品、食品まで、お得な価格で手に入れることができます。
しかし、それが逆に災いして、ついつい買いすぎてしまうのが店員あるある。
家の中が自社の商品であふれかえり、家族から「また新しいシャンプー?」と呆れられることも。
しかし、新商品をいち早く試せるのは、この上ない喜びです。
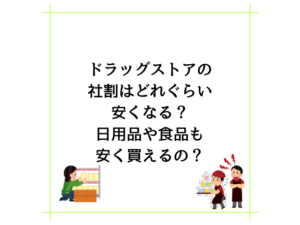
休憩時間5分前に、謎の連帯感が生まれる
お昼休憩や夕方休憩に入る直前、「あと5分で休憩だね!」と、パート仲間や社員とアイコンタクトを交わす瞬間。
このわずかな時間の中で、謎の連帯感が生まれます。「あと少し頑張ろう!」という無言のメッセージを送り合い、最後のひと踏ん張りをします。
そして、休憩時間に入ると、皆一斉に休憩室へ向かい、まるでタイムアタックでもしているかのように、猛スピードでご飯を食べるのです。
どの店舗に行っても、ついつい品揃えをチェックしてしまう
休日、プライベートで他社のドラッグストアに行くと、職業病が発動します。
商品の陳列方法や品揃え、POPの書き方などを無意識にチェックしてしまうのです。
「ああ、うちの店の方がこの商品は安いな」「ここの棚の並び、見やすいな」などと、まるで市場調査をしているかのように店内をウロウロ。
他店から学びを得ることもあれば、自分の店舗の素晴らしさを再確認することもあります。
お客様からの「ありがとう」が、何よりのエネルギー
仕事で疲れていたり、大変なことがあったりしても、お客様から「ありがとう」と笑顔で感謝の言葉をいただけると、一日の疲れが吹き飛びます。
「この前教えてくれた薬、すごく効いたよ」「いつも親切にしてくれてありがとう」といった言葉は、私たちにとって何よりのエネルギー。
この瞬間のために、毎日頑張っていると言っても過言ではありません。
ドラッグストア正社員とパートの違いから見る「あるある」

ドラッグストアの仕事は正社員かパートかによってもそれぞれ視点が違います。
ここではそれぞれの違いからあるあるをまとめてみました。
正社員・パート勤務形態別のあるある
正社員のシフト管理は、まるでパズルのよう
正社員が担当するシフト管理は、まるで難易度の高いパズルのよう。
パートさんの希望休や勤務時間、店舗の売上予測などを考慮しながら、最適な人員配置を考えなければなりません。
急な欠勤者が出た時には、代わりに勤務してくれる人を探すのに奔走し、頭を悩ませます。
すべてがうまくハマった時の達成感は大きいですが、常に「誰がどこにいるか」を把握しておく必要があります。
パートの、シフトを把握する能力は異常
パートさん同士の「〇〇さん、今日休みなんだね」という会話は日常茶飯事。
パートさんは、自分たちのシフトだけでなく、他のパートさんのシフトも把握していることが多いです。
これは、急な用事や体調不良でシフトを交代してもらう可能性があるため、自然と身につく能力。
お互いの勤務状況を把握することで、円滑なコミュニケーションや助け合いにつながっています。
正社員とパートの、お互いに対する気遣い
正社員は、パートさんが働きやすいように、無理のないシフトを組んだり、休憩をきちんと取れるように配慮します。
一方で、パートさんは、社員が忙しそうな時や、人手が足りない時に、積極的に手伝いを申し出たり、自ら進んで業務をこなしたりします。
お互いに「お疲れ様」や「ありがとう」と声をかけ合い、助け合うことで、チームとしての一体感が生まれます。
正社員の、売上目標に追われる日々
正社員は、日々の売上目標や、特定商品の販売目標を常に意識しています。
売上が伸び悩んでいると、どうすればお客様の購買意欲を刺激できるか、必死に考えます。
POPを書き直したり、商品の陳列場所を変えたり、試行錯誤の毎日。目標を達成できたときの喜びは大きいですが、達成できなかったときの悔しさは、次の目標への原動力になります。
正社員の、本社からの電話にビクッとなる
正社員が経験するあるあるが、本社からの電話に一瞬ビクッとなること。
「何か問題でも起きたのか?」と身構えてしまいます。しかし、多くは売上報告や連絡事項の確認。
それでも、電話が鳴るたびに、心臓がドキッとするのは、責任感の表れなのかもしれません。
パートの、急な欠員に焦るも、何とかなる
パートさんが急な体調不良や家庭の事情で休んでしまうと、残されたメンバーは一瞬「どうしよう…」と焦ります。
しかし、お互いに助け合い、業務を分担することで、なんだかんだで一日を乗り切ることができます。
特に、レジが混雑した時などは、全員が協力してテキパキと仕事をこなし、その場を乗り切った時の達成感は格別です。
正社員・パート共通の、休憩室での雑談は癒し
正社員もパートも、休憩室で交わされる他愛ない雑談が、何よりの癒し。
仕事の話だけでなく、プライベートなことや、最近ハマっていることなど、おしゃべりする時間は、仕事の疲れを忘れさせてくれます。
お互いのことを知ることで、仕事での連携もスムーズになり、より良い職場環境を作り出すための大切な時間です。
ドラッグストア店員特有のキャリアに関する悩み
ドラッグストア店員はキャリア面でも悩みの尽きない業種でもあります。
理由は大きく以下の3つです。
- 市場価値が上がりにくい
- 不定休で土日休みが取りにくい
- 肉体労働で体力的な不安が大きい
市場価値が上がりにくい
ドラッグストア店員のスキルは、接客や品出し、在庫管理など、店舗運営に特化したものが中心です。
これらのスキルは、同業界での転職には有利に働きますが、他業界への転職を考えた場合、専門的な知識や資格がなければ、市場価値を証明するのが難しいという現実があります。
例えば、IT業界やコンサルティング業界で通用するような、汎用性の高いスキルを身につける機会が限られているため、「このままでいいのか」と将来に不安を感じる人も少なくありません。
自己成長を求めるなら、登録販売者や管理栄養士といった専門資格を取得するなど、キャリアアップに向けた能動的な努力が必要となります。
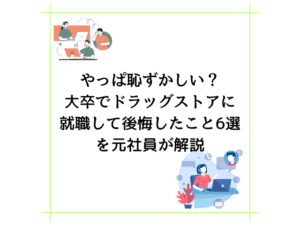
不定休で土日休みが取りにくい
ドラッグストアは、お客様が利用しやすいように、土日祝日も営業するのが一般的です。
そのため、従業員はシフト制で勤務することになり、不定休となります。
特に、土日や大型連休は人手が必要なため、希望休が通りにくいのが現状です。
家族や友人と予定を合わせるのが難しく、「なんでいつも私だけ休めないんだろう」と孤独を感じることもあります。
また、冠婚葬祭などの重要なイベントでも、シフトの都合で参加を諦めなければならないケースも出てくるため、プライベートとのバランスを保つことに悩みを抱える人は少なくありません。
肉体労働で体力的な不安が大きい
ドラッグストアの仕事は、一見すると立ち仕事が中心に見えますが、実はかなりの肉体労働です。
重い商品を品出ししたり、バックルームから大量の段ボールを運び出したりと、重労働を伴う作業が日常的に発生します。
長時間立ちっぱなしでいることも多いため、足腰に負担がかかりやすく、慢性的な疲労や腰痛に悩まされる人も少なくありません。
若いうちは体力で乗り切れても、年齢を重ねるとともに、この肉体的な負担が大きな不安要素となってきます。
特に女性や高齢になったとき、この仕事を続けられるのかと、キャリアの先行きを心配する声もよく聞かれます。
まとめ
毎日お客様と向き合い、大量の商品と格闘するドラッグストア店員の仕事は、決して楽ではありません。
肉体的な負担や、土日休みの取りにくさなど、キャリアに関する悩みも尽きないでしょう。
しかし、この「あるある」の数々は、私たちが日々どれだけ多くの経験を積んでいるかの証でもあります。
お客様からの「ありがとう」の言葉や、仲間との協力によって得られる達成感は、この仕事でしか味わえない特別なものです。
大変なことも、クスッと笑える「あるある」に変えて、これからもお客様の健康と暮らしを支えていきましょう。