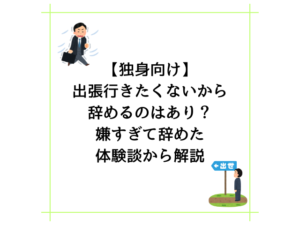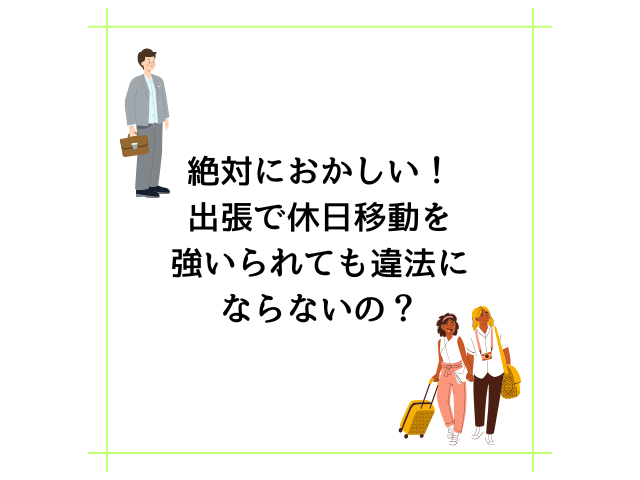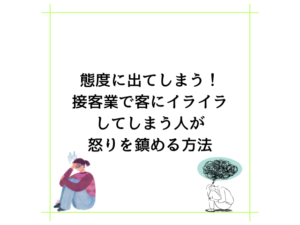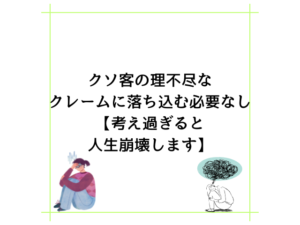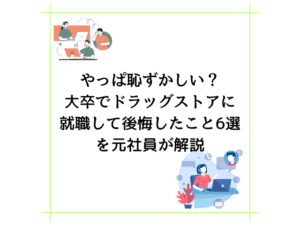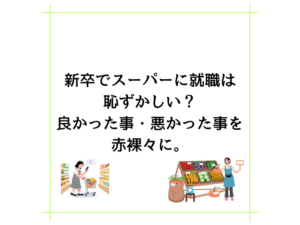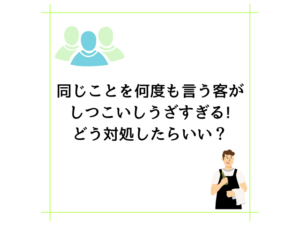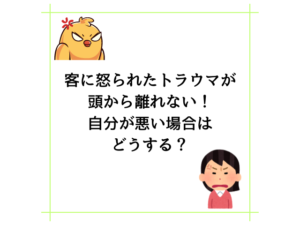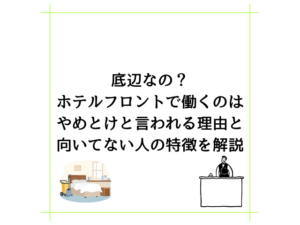土曜日の朝、新幹線や飛行機に揺られながら、ふと思ったことはありませんか。
- これ、仕事じゃないの?
- なんで貴重な休日を移動に使わなきゃいけないんだ?
出張で週末や祝日に移動を強いられる。
それなのに、会社からは「移動時間は労働時間ではない」の一点張りで、賃金どころか手当すら出ない。
この「出張 休日移動 おかしい」という不公平感は、多くのビジネスパーソンが抱える共通の悩みです。
「違法じゃないの?」と疑問に思うあなたの感覚は、決して間違いではありません。
本記事では、この休日移動が法的にどう解釈されるのかを明確にしつつ、なぜ「おかしい」と感じるのか、その根本的な理由を徹底分析します。
そして、あなたが会社に主張できる適切な対処法、会社が見直すべきルールまで具体的に解説します。
「出張の休日移動」が違法にならないのはなぜか?

「絶対におかしい!」と感じるあなたの気持ちは痛いほどよくわかります。
しかし、原則として出張の休日移動が「違法」にならないのには、日本の労働基準法における「労働時間」の定義が大きく関わっています。
労働時間の定義と「移動時間」の原則
まず、労働基準法でいう「労働時間」とは、単に会社にいる時間ではありません。
裁判所の判例や行政解釈に基づくと、労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」を指します。
この定義に照らし合わせると、出張中の移動時間は原則として労働時間と見なされないことが多いのです。
なぜなら、移動中の新幹線や飛行機の中では、以下のような「自由」が認められているからです。
- 睡眠、読書、映画鑑賞など、私的な活動ができる。
- 業務上の報告・連絡が義務付けられていない限り、時間の使い方は基本的に本人の裁量に委ねられている。
会社から明確な業務指示がなく、単に目的地へ向かっているだけの時間は、「私生活に属する時間」または「移動に必要な準備時間」と解釈されるため、「指揮命令下にある時間」とは認められにくいのです。
これがおかしいと感じても、法的に原則として会社が賃金を支払う義務がないとされる最大の理由です。
例外!移動時間が「労働時間」になるケース
しかし、これはあくまで「原則」です。
あなたの移動時間が「労働時間」として認められ、会社が賃金を支払う義務が生じる例外的なケースも存在します。
具体的には、移動中であっても「使用者の指揮命令下にある」と判断される状況です。
労働時間となる具体的なケース
移動中の明確な業務指示がある場合
- 上司から「新幹線の中でこの会議資料を完成させておけ」と具体的な作業を命じられた。
- 移動中に顧客や取引先への電話・メール対応が必須とされ、それが移動中しかできない状況にあった。
運転業務を命じられている場合
長距離の移動であっても、会社から「車を運転して移動せよ」と命じられている場合、その運転時間は完全に会社の指揮命令下にあると判断されます。
(ただし、自身が運転しない同乗者はこの限りではありません)
重要な荷物や機密情報の監視を命じられている場合
移動中、機密文書や高価な機器を厳重に管理・監視する義務があり、その緊張から解放されない場合。
これらの例外的なケースに当てはまる場合は、移動時間であっても労働基準法上の「労働時間」として扱われ、会社は休日労働に対する賃金(割増賃金)を支払う義務を負います。
あなたの出張移動が上記の例外に該当しないか、今一度チェックしてみてください。
もし該当するなら、それは「違法ではない」で済まされない問題となります。
なぜ「おかしい」と感じるのか?その根本的な理由

法律の解釈上、休日移動が「労働時間ではない」とされても、あなたの「絶対におかしい!」という感覚は全く間違っていません。
このモヤモヤは、法的な定義と現代社会における時間の価値との間に生じた大きなズレから発生しています。
「時間の拘束」に対する対価がない不公平感
「移動時間は自由」という法律の建前は、多くのビジネスパーソンの実態と乖離しています。
あなたが「おかしい」と感じる根本は、「私的な時間を強制的に奪われている」という事実に対する対価の不在です。
- 真の自由の不在: 移動中、あなたは確かに寝ることもできますが、「どこでも行ける」「誰とでも会える」という休日の真の自由は完全に制限されています。目的地への到着という会社のミッションに縛られ、移動手段や時間に拘束されている状態に変わりはありません。
- 家族・私生活への影響: 移動に往復8時間かかれば、家族と過ごすはずだった丸一日、趣味に費やす予定だった時間を失います。この失われた機会費用に対して、会社は原則として何も補償していません。
労働の対価としての「賃金」は出なくても、時間的拘束に対する「慰労」や「補償」が一切ないことが、社員に「会社にぞんざいに扱われている」という不公平感を抱かせるのです。
会社側の「配慮不足」が不満を増幅させる
この不公平感を増幅させているのが、多くの日本企業における「配慮」の欠如です。
- 日当(移動手当)の廃止・低額化: かつて日当は出張中の精神的・肉体的負担の補填として機能していましたが、経費削減の流れで廃止されたり、極めて少額(数百円程度)に抑えられたりしているケースが散見されます。この「微々たる補償すらしない」姿勢が、社員の不満を爆発させます。
- 「ご苦労様」の一言の欠如: 休日移動を強いたにもかかわらず、上司や会社から移動に対する労いの言葉や感謝がない場合、社員は「自分の時間は会社にとってタダのコストでしかない」と感じ、エンゲージメントが著しく低下します。
企業が「移動時間は労働時間ではないからOK」という法的な盾の裏に隠れ、社員の心身の負担を無視しているように映ることが、「おかしい」という感情の正体です。
法改正の動きと社会的な価値観の変化
現代社会では、働き方改革やリモートワークの浸透により、「時間」そのものの価値が大きく見直されています。
「勤務時間外は個人の時間」という意識が強まる中で「サービス移動」という旧態依然とした慣習は時代錯誤と見なされ始めています。
優秀な人材ほど、自分の時間や私生活を重視します。
休日移動を当たり前とし、何の補償もしない企業は、「社員の時間よりも会社の都合を優先する」というメッセージを発しており、結果的に人材流出のリスクを高めているのです。
あなたの「おかしい」は、時代の変化を映す正当な感覚なのです。
会社員が取るべき適切なアクション
「おかしい」と感じるだけで終わらせず、不公平な状況を変えるためには、感情論ではなく、法的な知識とロジックに基づいた適切な行動が必要です。
会社員として、あなたが出張の休日移動に対して取るべきアクションを解説します。
まずは移動中の「業務指示」の有無を明確にする
前述の通り、休日移動が労働時間になるかどうかの最大の分岐点は、「使用者の指揮命令下にあるか」です。
この点を曖昧にせず、移動前に上司と明確に確認を取りましょう。
- 移動中の業務指示の確認: 上司に対し、「移動中に資料作成や電話対応などの業務を行う必要はありますか?」と書面(メールやチャット)で確認しましょう。
- 明確な業務指示があった場合: もし「◯◯の資料を新幹線で仕上げておいて」などと指示があった場合は、その指示の記録(メールのスクリーンショットなど)を保存してください。これは、後に賃金や代休を請求する際の重要な証拠になります。
- 証拠の記録の習慣化: 実際に移動中に作業を強いられた場合は、開始時間と終了時間、作業内容をメモや勤怠記録に記録しておきましょう。
この一手間で、あなたの移動時間は「自由時間」ではなく「労働時間」へと法的に立場を変える可能性があります。
会社への交渉は「賃金」だけでなく「休暇」を軸に
直接的に「賃金を払え」と要求するのは、社内で角が立つ場合があります。
まずは会社側も受け入れやすい代替案、つまり「休暇」を軸に交渉してみましょう。
- 代休・特別休暇の取得を提案する: 休日移動で失われた時間(例:往復8時間)について、「平日に特別休暇として相応の時間をいただきたい」と交渉します。これは、会社にとっては人件費(割増賃金)を支払うよりコストが低く、受け入れやすい案となる場合があります。
- 出張手当(日当)の見直しを求める: 賃金ではなく、あくまで「慰労・雑費補填」という名目の日当の増額や新設を提案します。他社の事例(業界平均など)を提示し、ロジックで交渉することで、単なるワガママではないと理解してもらいやすくなります。
交渉は感情的にならず、「社員のモチベーション維持」と「企業のコンプライアンス順守」という二つの視点から提案するのが効果的です。
泣き寝入りしないための最終手段
社内での交渉が難航したり、明らかに違法なサービス移動を強要され続けたりする場合は、外部の機関に相談することも視野に入れましょう。
- 労働基準監督署への相談: 移動中に業務指示があったことを示す証拠(前述の記録)がある場合、労働基準監督署(労基署)に相談に行くことができます。労基署は、会社に対して是正勧告を行う権限を持っています。
- 弁護士などの専門家への相談: 労働問題に詳しい弁護士に相談することで、法的なアドバイスを受けたり、会社との交渉を有利に進めたりすることが可能です。
「おかしい」と感じたまま諦めるのではなく、適切な手段で声を上げることが結果的に会社全体の働き方を変える一歩につながります。
企業が今すぐ見直すべき「出張の休日移動」ルール
社員が「おかしい」と感じる不公平感を解消し、優秀な人材の流出を防ぐためには、企業側が旧態依然とした慣習から脱却し、ルールを見直すことが急務です。
ここでは、企業が今すぐ取り組むべき具体的な対策を解説します。
移動手当(日当)は「福利厚生」と心得よ
多くの企業が誤解していますが、日当(出張手当)は労働の対価である「賃金」ではありません。
これは、出張に伴う精神的・肉体的疲労への慰労や、出張先の雑費を補填するための「福利厚生」としての役割を果たすべきものです。
- 日当の位置づけを再定義する: 「労働時間ではないから手当も不要」という考え方を捨て、「休日に会社の都合で時間を拘束したことへの感謝と補償」として日当を支給するルールにしましょう。
- 相場を参考に金額を見直す: 日当の相場は企業規模や役職で異なりますが、多くの企業では1日あたり2,000円〜5,000円程度が目安です。現状、日当がない、または極端に低い場合は、社員の慰労を目的として金額を見直すべきです。
- 「無形の対価」を言語化する: 手当を出すことが難しい場合でも、上長が「休日に移動してくれてありがとう」「ご家族に迷惑をかけて申し訳ない」といった感謝の言葉をかけることを義務付けましょう。この「無形の対価」が、不公平感を和らげる重要な要素となります。
労働時間か否かの「グレーゾーン」をなくすためのルール作り
最もトラブルになりやすいのは、移動時間が「労働時間」なのか「自由時間」なのかが曖昧な「グレーゾーン」です。
この曖昧さを排除する明確なルール作りが求められます。
- 事前申請・承認制の徹底: 休日移動を社員に命じる際は、必ず上長の事前承認を得ることを必須とし、その申請書に「移動中の業務指示の有無」を明確に記載する項目を設けましょう。
- 「業務指示の禁止」を明文化: 移動中は原則として業務を禁止することを就業規則や出張規定に明文化します。これにより、社員は安心して私的な時間を過ごすことができ、会社は「指揮命令下にない」ことを明確に主張できます。
- 例外的な業務指示の記録義務: やむを得ず移動中に業務を指示する場合は、その作業時間、内容を記録させ、後で必ず代休や賃金として清算する仕組みを構築します。
休日移動を最小限にするためのオペレーション改善
根本的な解決策は、休日移動そのものを最小限に抑えることです。
- 移動の「平日化」を優先する: 出張スケジュールを組む際、移動は可能な限り平日の労働時間内に行うことを最優先事項とします。月曜日の朝一の会議であれば前日の日曜移動を強制せず、前日の夕方に移動するよう指示するなど、会社都合で社員の休日を削らない配慮が必要です。
- オンライン会議の活用: 現地集合が本当に必要かを再検討します。リモートで済ませられる会議はオンラインに切り替えるなど、出張自体の回数を削減する努力も重要です。
企業がこのような具体的な配慮を示すことで、「おかしい」という不満は「配慮のある会社」という信頼感に変わり、社員のモチベーションと生産性を維持することにつながります。
まとめ
出張の休日移動は、原則として法的に「違法」ではありません。
しかし、「労働時間ではないから賃金も手当も不要」という企業側の姿勢が、社員の「絶対におかしい」という強い不公平感を生み出しているのです。
あなたの「おかしい」という感覚は、時間の価値を重視する現代においては極めて正当なものです。
企業がすべきは、法律の解釈を盾にすることではなく、日当の支給や代休の付与といった具体的な配慮を示すことです。
それが、優秀な人材の離職を防ぎ、社員の信頼とエンゲージメントを維持する唯一の道です。
会社員であるあなたは、移動中の業務指示の有無を明確に記録し、感情論ではなくロジックで対話を進めましょう。
あなたの小さな行動が、会社の不公平な慣習を変え、より健全な働き方につながるはずです。